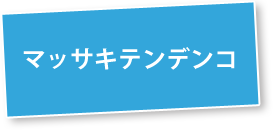後世に伝えたいこと
無事逃げ切り!…妻がまだ帰っておらず
2011年(平成23年)3月11日午前中は何も変わりなく、まったく平凡な平和な日だった。いつもと同じ平和な社会が地獄と化す午後2時46分。今までに経験のない大きな大きな揺れの地震!長~い長~い地震!これは津波だっ!!!と直感 絶対に津波が来るぞっと直感!まず家族に声をかけ車(軽4輪車)を高台に移動する。 いつの地震でもこの行動は変わらない。高台は海岸より直線距離で200m位にあり、三面椿※1のある中森熊野神社の境内である。海抜1 5m位。自宅はその中間地点にある。非常持ち出し品などを持ち、療養で帰省中の娘を避難した軽自動車に連れて行く。それでもまだ時間があると感じ、自宅に戻り戸締りをして、避難した。今回は車を避難させてから直ぐに停電状態だった。店舗併用住宅の店のシャッターは電動が効かなかったので手動でシャッターを閉めた。(伯宅に戻ることと、その後の行動は危険を伴うので今後は慎むべきと反省している)高台に避難させた車の付近で、海の変化を見ながら「津波は来ないだろう」と、「いや、 来てくれるな」と願いながら…。あちこちから地域の人々が避難してくる。みな心配そうな、不安顔した人々。口々ににんなに大きな地震は今までには知らない!」。「こんな大きな揺れは今までに経験がないな」「これは津波が来るぞっ」などなどつぶやきが飛び交う。
春3月とはいえ寒い日だった。陸前高田※2の整形外科に通院していた妻が帰宅していない。携帯も通じず連絡が取れない。防災無線はサイレンが鳴り大津波警報発令を放送している ようだが頭に入らない。妻は帰って来てないし、関東にいる息子にも携帯をかけても通じ ない。何回も電話とメールをする。何回かのうちに息子にメールが通じた。「無事逃げ切り」という電文のような奇跡のメール。 詳しいことをメールする余裕などなく、このような電文を送ったのが届いていた。送信時刻は3月11日午後3時16分と通信記録に残っていた。この記録は息子が保存して現在も残っている。 メールが通じてから5分位経った頃妻の車が高台へ向かって登ってきた。無事に帰ってきた!!ともかく家族全員3名とも生存の確認ができ、まず一安心。
後日談になるが、当時のメールのことを話題にして「全員逃げ切り」じやなかったんだね。と当時の状況を思い出し、笑い話にされている。
※1三面椿…マッサキ内にある古椿(詳細) ※2…マッサキ町のすぐ隣りにある市
どす黒い鉛色
家族の安否が解って一安心して間もなく、泊里湾※3の方を見ると黒いような白いような鉛色のような波が入り混じり、湾の西側の岩に大きなうねりが見えて、あたかも生き物が動いてるような異様な動きを見た、「ああこれが津波か」と思い 「ここまでは来ないだろう」との変な期待と想像を以って波の動きを眺めていた。と同時に足元まで来るんじゃないかとの不安もよぎり始め、更に高い方へと動きながら海を見つめていた。林や家の陰で湾が全部は見えないが、時計回りの動きがあったように見えた。泊里地域一帯が津波に呑まれ陸の家々も水没になった。その頃我が家の隣の家が東の方へ流れていくのが見えた。家の形がそのままで…やがて今度は赤い屋根の親戚の家が西へ向かって流されるのを見た。入潮と引き潮がぶつかり渦巻き状態も起きたようだ。避難している人々の悲鳴やら、驚きの声やら津波の音やらで騒然として、筆舌に尽くしがたい寂しさと不安を感じた。時すでにタ方。気温も下がり、無情にも雪がちらちらと降り寂しさに輪をかけられ、只呆然と立ちすくんでいた。
津波の音も止み、水も引けて地面が見えてきたので、下の方へ降りて我が家を見に行ったら木造部分は全部流され影も形もなく、店舗部分の鉄骨だけが残っていた。壊れた建物、瓦礫が散乱、泥水、車の残骸、ごみの山、道路は瓦礫瓦礫で通れない。この世の地獄とはこのことかと…寒さと不安との思いで日暮れを迎えた。これからどうすればいいのか、今晩は何処で泊まれるのか、これからどうして生きていけるのか一寸先は闇。
その時誰かが叫んだ。「みんなコミセン※4に集合だって」との声。(コミセンとは地域のコミュニティセン ターの事)続々と地域の人々が集まりたちまち大集団ができた。その晩はまず一睡もでき ない状態で一夜を過ごした。食事は被災しなかった人々が持ち寄りおにぎり1個、衣類(毛 布、布団類)はお寺さんからの支援。また民宿やホテルなどの協力もあり何とか一夜を過 ごした。
一夜明けた3月12日おにぎりが配られ朝食は何とか過ごす。しかし昨日の人数にまた避難者が増え泊里※5の人々は碁石※6公民館へと移動。私たちは碁石公民館で2泊。次の日から三十刈※7民館に移動。人々はそれぞれ3か所に分宿となる。私の家族は三+刈公民館で二ヶ月余りお世話になった。一週間以上も着のみ着のままで寝る。歯磨き洗顔なども思うようにならず、大変な経験をした。それでも生きた人はいい、不運にも犠牲にな った方や行方不明者もあり、そんな家族と共に沈痛な思いの時間を共有した。三十刈公民館での二ヶ月余りの生活は、まさに人々の絆の大切さ、有難さを身を以って体験した。館長以下役員会員の皆さんには、朝タ見回り、気配りと本当にお世話になりました。同年5月18日大田仮設住宅※8へ入居するまでお世話になり、その間物心両面のご援助には本当に有難く感謝感謝で一杯です。有難うございました。
大田仮設住宅には約130世帯の集団で2年半ほど暮らしてきました。お互いが力になり、また協力し合い元気を貰い、悲しんでばかりもいられないので楽しみながらの期間でした。本当に感謝感謝でした。いつの日か我が家に転居できる日を夢見て暮らしたのも、辛さを半減させてくれたようにも思います。
※3泊里湾…マッサキ内にある湾の一つ ※4コミセン…多目的な施設。ぎりぎり被災をまのがれた。 ※5泊里…地区名 ※6碁石…地区名 ※7三十刈…地区名 ※8大田仮設住宅(市営球場)…大田地区に設置された仮設住宅で、元々は大船渡市営球場。
つながりこそ最大の財産
津波の犠牲者を出さないためには、地震が起きたらまず高台へ避難すること。これに限ります。家族の安否、テレビ、ラジオの情報収集、電話連絡、メールなどはその次です。今回はそのことを強く学び深く感じています。
津波当日から地域の皆さんのお世話になり、また全国、全世界の皆さんからのご支援を頂き何とか現在を迎えていますが、日頃の地域の緯、コミュニティーがいかに大切か。地域の繋がりがあればこそ、避難所生活もスムースに運んだと思います。過去50年も前からこの泊里地域には五つの行政区がーつになる防災組織があります。泊里地域振興協議会です。今はやりの自主防災組織の先駆けともいうべき組織です。地域内の共有する諸問題の解決。地域内の有事の時はお互いが協力しあう長い間の絆が、今回大きな力となったことは特筆すべき事であり、津波の伝承とともに伝え続けなければならないと思います。
また、遠方の見知らぬ方々からも暖かい心のこもった応援をして下さり、その輪がますます大きくなり、今現在も物心両面で支援を頂き絆ができてきて居ります。いつの日かお会いできる日を楽しみにしていましたが実現しそうです。素晴らしい三陸海岸と復興した大船渡を見て頂くことを夢に健康第一と精進したいものと思っています。
2016.04記

- MTDファイル No.3
小松 基さん - マッサキ内で、長年呉服店「まるふく」を経営。震災時は、通常通り営業していた。なんとか難を逃れたが、住居を流出。避難所、仮設で過ごし、その間、多くのボランティアのふれあいがあった。数年前に自力再建を果たしたが、その後もボランティアとのつながりを大切にしている。